ピロリ菌
ピロリ菌とは
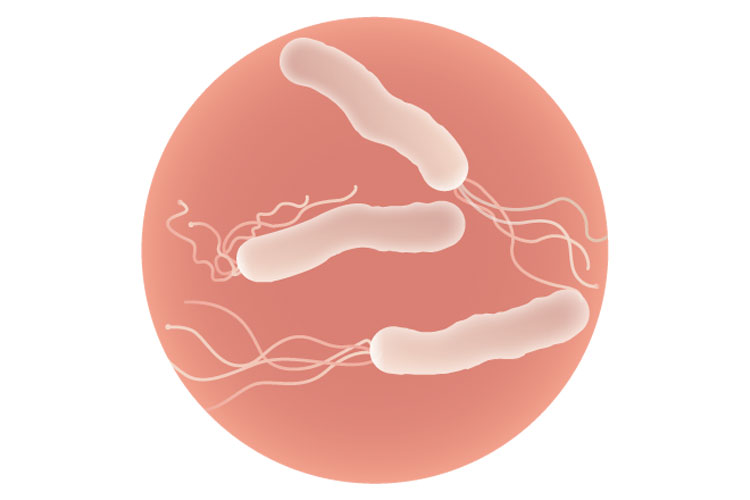
一般的にピロリ菌と呼ばれている菌の学名は、Helicobacter pylori(ヘリコバクター ピロリ)といいます。「らせん」とか「旋回」という意味の、ヘリコプターのヘリコと同じで、菌がもつ鞭毛と呼ばれる部分を回転させて移動。バクターとはバクテリア(細菌)という意味なので「らせん状の鞭毛をもつ細菌」という意味です。ピロリとは胃の出口(幽門)をさす「ピロルス」からきています。この菌は胃の幽門部(胃の出口付近)から初めて見つかりました。
ピロリ菌の最も大きな特徴は、酸素の存在する大気中では発育しないことで、酸素にさらされると徐々に死滅します。乾燥にも弱く、グラム陰性桿菌に分類されます。
大きさは0.5 × 2.5~4.0μmで、数本のべん毛を持ち、胃の中を移動します。ピロリ菌が強酸性下の胃の中で生育できるのは、胃の中にある尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解し、アンモニアで酸を中和することにより、自分の身の周りの酸を和らげて生きています。
現在の国内感染率は35%(3500万人)、ピロリ菌が原因での胃がんへの進展は年率0.5%(10年で20人に一人)と言われています。
ピロリ菌の感染で発症する主な症状
ピロリ菌に感染すると、胃の炎症が引き起こされ、さまざまな消化器系の症状が現れることがあります。ただし、自覚症状がないケースも多く、気づかないうちに進行することもあります。
胃痛
ヘリコバクター・ピロリ菌(H. pylori)に感染した人のほぼ全員に胃炎が認められますが、通常、自覚症状は乏しく、ただの胃痛として現れることが多いです。食事の影響やストレスと区別がつきにくいことも特徴です。
吐き気・嘔吐
胃の炎症が進行すると、吐き気や嘔吐を伴うことがあります。ただし、これらの症状はピロリ菌に感染していなくても起こるため、単独での判断は難しいです。
胸焼け
胃酸の分泌が不安定になり、胃の粘膜が刺激されることで胸焼けを感じることがあります。特に空腹時や食後に症状が出やすいのが特徴です。一般的にいわれる逆流性食道炎等でも同じような症状を呈することがあります。
おなら
胃の状態が悪化すると消化不良を引き起こし、腸内環境の変化によりガスが溜まりやすくなります。その結果、おならの量が増えることがあります。
口臭
ピロリ菌による胃炎が進行すると、胃の働きが低下し、胃の内容物が長く滞留することで口臭が強くなることがあります。特に、朝起きた時に感じやすいのが特徴です。
げっぷ
胃の炎症や胃酸の逆流により、げっぷが頻繁に出ることがあります。特に脂っこい食事や刺激の強い食事の後に出やすくなります。
ピロリ菌感染が原因となる病気
なぜピロリ菌感染が困るのかというと、感染状態が持続することで下記のような疾患(病気)が引き起こされ、それにより様々な症状が出現します。
胃炎
ピロリ菌に感染すると胃液や胃酸を分泌する細胞にダメージをうけ、胃粘膜に慢性的な炎症を引き起こします。この持続的な炎症状態が、胃粘膜の萎縮や腸上皮化生を促進し、粘膜の防御機能をさらに低下させます。これにより、胃酸や消化酵素による自己消化が進行し、細胞のDNA損傷や再生を繰り返すことで、潰瘍や胃がんのリスクにもなります。
胃・十二指腸潰瘍
ピロリ菌は「ウレアーゼ」という酵素を産生し、胃内の尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解します。このアンモニアは胃酸を中和し、菌が生存しやすい環境を作りますが、同時にアンモニア自体が胃粘膜を直接刺激し、損傷を引き起こします。またピロリ菌はコレステロールを取り込み、炎症をきたす物質を産生し、これが直接粘膜を傷害すること知られています。
胃炎が悪化し、胃の壁の傷害がつよくなると潰瘍になります。
胃がん
先にしめしたように胃炎や胃潰瘍などの炎症の悪化が原因になることや、ピロリ菌のもつ特殊な蛋白(CagA)が胃の細胞に注入されることで、胃の粘膜の細胞サイクルに異常をきたし、さらに胃がんのリスクを高めることが科学的に証明されています。
胃MALTリンパ腫
胃MALTリンパ腫は低悪性度のリンパ腫(血液の癌)の一つとして知られています。
胃の慢性的な炎症を背景に、B細胞リンパ球が増殖と癌化をおこし、胃に様々な形態の潰瘍や炎症所見が現れ、発見されることが多い疾患です。胃MALTリンパ腫の約90%の症例でピロリ菌感染が認められています。
ピロリ菌感染が確認された胃MALTリンパ腫の患者に対しては、第一選択としてピロリ菌の除菌療法が行われます。この治療により、約60~90%の患者でリンパ腫の寛解が得られることが報告されています。 一方、ピロリ菌感染が認められない場合や、除菌療法が効果を示さない場合には、放射線療法などの他の治療法が検討されます。
特発性血小板減少性紫斑病(ITP)
特発性血小板減少性紫斑病(ITP)は、自己免疫反応により血小板が破壊され、出血傾向を引き起こす疾患です。近年、ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)感染との関連性が注目されています。
ピロリ菌の抗原と血小板膜上の抗原が類似しているため、ピロリ菌に対する免疫応答が自己免疫反応を引き起こし、血小板が誤って攻撃される可能性などが提唱されていますが、明確な理由は不明です。
ITPの患者さんのピロリ菌感染者の約半数以上で、除菌により血小板数の増加が見られます。
ピロリ菌はいつ感染する?
多くは幼少期に感染するとされています。これは、幼少期にはまだ胃の発達が不十分で、胃酸の酸性度や免疫機能が確立されていないためです。かつての日本は上下水道が完全には普及しておらず、井戸水などから感染していたこともありますが、現在の日本では、ほぼ飲み水からの感染はないと言えるでしょう。
現在は、家庭内感染、すなわち親族からの経口感染(口移しでの感染)が主流です。
家庭内での口移しや食器の共有
ピロリ菌に感染している大人が、食べ物を口移しで子どもに与えたり、スプーンなどの食器を共有することで、菌が子どもに伝播する可能性があります。
他に、稀ではありますが成人になってからも感染するケースがあります。上下水道の整備が不十分な地域(山間部や海外の発展途上国)において、汚染された水や食べ物にピロリ菌が混入し、それを摂取することで感染することがあります。
日本でも戦前戦後は、上下水道が整備されておらず、ピロリ菌の混入した水や、食べ物を介して感染するケースがあり、現在の70〜90歳代の方にピロリ菌陽性者が多いのはそのためです。現代の日本では、水道水等から感染するケースはほぼありません。
感染の多くは乳幼児期
ほとんどが離乳食期などに親から子へ口移し等で感染するケースが多いと言われています。免疫力が未熟で胃酸の分泌が少ないため、ピロリ菌が胃の粘膜に定着しやすく、感染の多くは5歳以下で生じると考えられています。
感染経路
ピロリ菌は主に人から人へと感染し、生活習慣や環境によって広がることが知られています。特に家庭内での接触や飲食物を介して感染するケースが多く、成人になっても上下水道の整備が未発達の地域では、汚染された水や食べ物を介して感染するケースがあります。
家庭内感染
ピロリ菌に感染した大人が、離乳食を口移しで与えるなどの行為を通じて、乳幼児に感染させる可能性があります。
衛生環境
井戸水などの汚染された水や食物を摂取することで感染する場合があります。 日本では、衛生環境の改善により若年層の感染率は低下していますが、50代以上の世代では幼少期の環境により感染率が高い傾向があります。
また、発展途上国といった海外地域では未だに上下水道が整備されていない地域もあり、そういった所で仕事をしたり旅行したりした際に感染する可能性はあります。
ピロリ菌の検査方法
ピロリ菌感染の有無を調べるためには、以下の検査方法があります。
下記に示しますが、簡便で感度や特異度といった観点から、尿速呼気検査や血液からピロリ抗体をチェックする方法が多く実施されています。
既にピロリ菌の感染が判明している場合でも、除菌治療を行うに当たっては内視鏡検査は必須事項となっています。
最も大事なのは、ピロリ菌感染により胃炎が進行し、既に「胃がん」ができている場合があることです。
胃がんが判明した場合は、早急にそちらの治療に取り掛かる必要があるため内視鏡検査はとても重要です。
内視鏡を用いる検査方法
内視鏡を使った検査では、胃の粘膜を直接観察し、胃炎以外にも他に疾患がないか検索します。
消化器内視鏡検査を多く行なっている施設や、消化器内視鏡専門医になると胃の表面を観察しただけで、現在ピロリ菌に感染しているのかどうかまで概ね判定ができます。(確定診断には、その他のピロリ検査は必須です)
内視鏡検査をした場合、その際に採取した組織を用いた各種検査によって、ピロリ菌の存在や特性を詳しく調べることが可能です。
迅速ウレアーゼ試験
胃から採取した組織を用いて、ピロリ菌が産生するウレアーゼ酵素の働きを確認します。
鏡検法
内視鏡で採取した胃粘膜組織を顕微鏡で観察し、ピロリ菌の存在を直接確認します。
培養法
胃粘膜組織を培養し、ピロリ菌の増殖を確認します。
核酸増幅法
胃液を含む内視鏡廃液中のピロリ菌DNAを検出し、抗菌薬の感受性も調べることができます。ただ、薬剤感受性のチェックは保険適応にはなっていません。現在、ピロリ除菌治療に用いられている抗菌薬に耐性を持っている患者さんが増えていることから、今後薬剤感受性の保険適応が可能となれば、さらにピロリ菌の一次除菌率があがることが期待されます。
内視鏡を用いない検査方法
内視鏡を使用しない方法では、採血や呼気、便などを用いてピロリ菌の感染を確認します。これらの検査は身体への負担が少なく、簡便に実施できるため、健康診断やスクリーニングにも広く利用されています。あくまで数値での検査結果になるので、胃炎の状況の把握や、胃がんの存在を把握するためには内視鏡検査は必須となります。
尿素呼気試験
特定の薬剤を服用し、呼気中の二酸化炭素の変化を測定することで、ピロリ菌の感染有無を調べます。
抗体測定法
血液や尿を用いて、ピロリ菌に対する抗体の有無を調べます。
糞便中抗原測定
便中のピロリ菌抗原の有無を調べます。
ピロリ菌検査のまとめ
これらの検査方法は、それぞれ特徴や利点があります。例えば、尿素呼気試験は非侵襲的で簡便なため、広く用いられています。
また、抗体検査法(血液)も会社の健診や足立区の胃がんハイリスク検診でも用いられております。
一方、内視鏡を用いる方法は、胃の状態を直接観察できるため、詳細な診断が可能です。検査の選択は、患者さんの症状や状況に応じて医師が判断します。ピロリ菌感染が確認された場合、適切な除菌治療を行うことで、胃潰瘍や胃がんのリスクを低減できます。
ピロリ菌は自然治癒する?
ピロリ菌に感染した場合でも、通常でかかる抗生物質などで自然に消えることが10%前後あるといわれています。これは自然除菌と呼ばれ、内視鏡検査をうけた際にピロリ菌に感染していたであろう、胃粘膜の所見があるにもかかわらず、除菌したことがない患者様が一定数いることが全国的に報告があります。
しかし、こういった症例はすくなく、ほとんどは除菌治療が必要です。 まずは感染の有無を確認し、感染が判明した場合は早めに除菌治療を受けましょう。
ピロリ菌の除菌について
ピロリ菌の除菌治療には、胃酸の分泌を抑制するお薬と2種類の抗生物質の3つのお薬が用いられます。この三種類のお薬を一週間服用することで、約8割の方は1回目の内服治療で、除菌に成功すると報告されています。そして場合に応じて胃の粘膜を保護する薬剤を併用します。
1回目で除菌がうまくいかない(ピロリ菌が退治できない)患者様が2割程度存在します。
その方は内服する抗生物質を変更し、2次除菌(2回目)を行います。
現在の日本では、2次除菌まで保険適応となっていますが、それでもピロリ菌が除菌できない、消えない患者様が存在します。
これは、今まで生きてきた中で風邪などを引いた際に、抗生物質などを処方されることが多かったりすると、ピロリ菌に耐性ができ、除菌治療で用いられる抗生物質が効果をしめさなくなっています。
3次除菌以降は、自費診療として扱われております。
その際は、病院によってピロリ菌を採取し、どの抗生物質が効くのかを大学病院等の限られた専門の施設で調べた上で行うことが多くなっています。
除菌に成功したからといって、胃がんなどの病気にならないわけではありません。ピロリ菌に感染している期間が長いと、胃の粘膜が正常に戻るのに時間がかかるからです。除菌後も定期的に内視鏡検査などを受け、胃の状態を確認しましょう。
ピロリ菌の除菌治療の際に生じる症状
除菌治療を行う際に、普段、風邪をひいたりして病院に受診して処方してもらう場合よりも、かなり多い容量の抗生物質が用いられます。抗生物質の種類も2種類となるため、通常よりも「薬の内服による副作用」が生じやすい状況となります。
頭痛
ピロリ菌感染自体が頭痛を引き起こすことはほとんどありません。しかし、除菌治療で使用する抗生物質の影響で、一時的に頭痛が起こることがあります。
発熱
ピロリ菌感染によって発熱することは稀です。ただし、除菌治療中に体の免疫反応として微熱が出ることがあります。特に抗生物質による影響が考えられます。
下痢
ピロリ菌感染そのものが下痢の直接的な原因になることはほとんどありません。しかし、除菌治療で使用する抗生物質が腸内環境に影響を与え、一時的に下痢や軟便を引き起こすことがあります。治療中は整腸剤を併用することが推奨される場合もあります。
発疹
アレルギー反応の一部として、体に薬疹とよばれる多様な発疹が出現する場合があります。これもどの薬でも生じる可能性は秘めていますが、除菌治療の際は内服する抗生物質の量や種類も多いため、体に異常が出た際は、一度内服を中断し、医師に相談してください。
まとめ
当院には足立区でも数の少ないH.pylori(ピロリ菌)感染症認定医も在籍しております。
このため、ピロリ菌陽性となった患者様や除菌した既往のある患者様に対して、詳細なフォローや治療が可能です。
お気軽にご相談ください。
